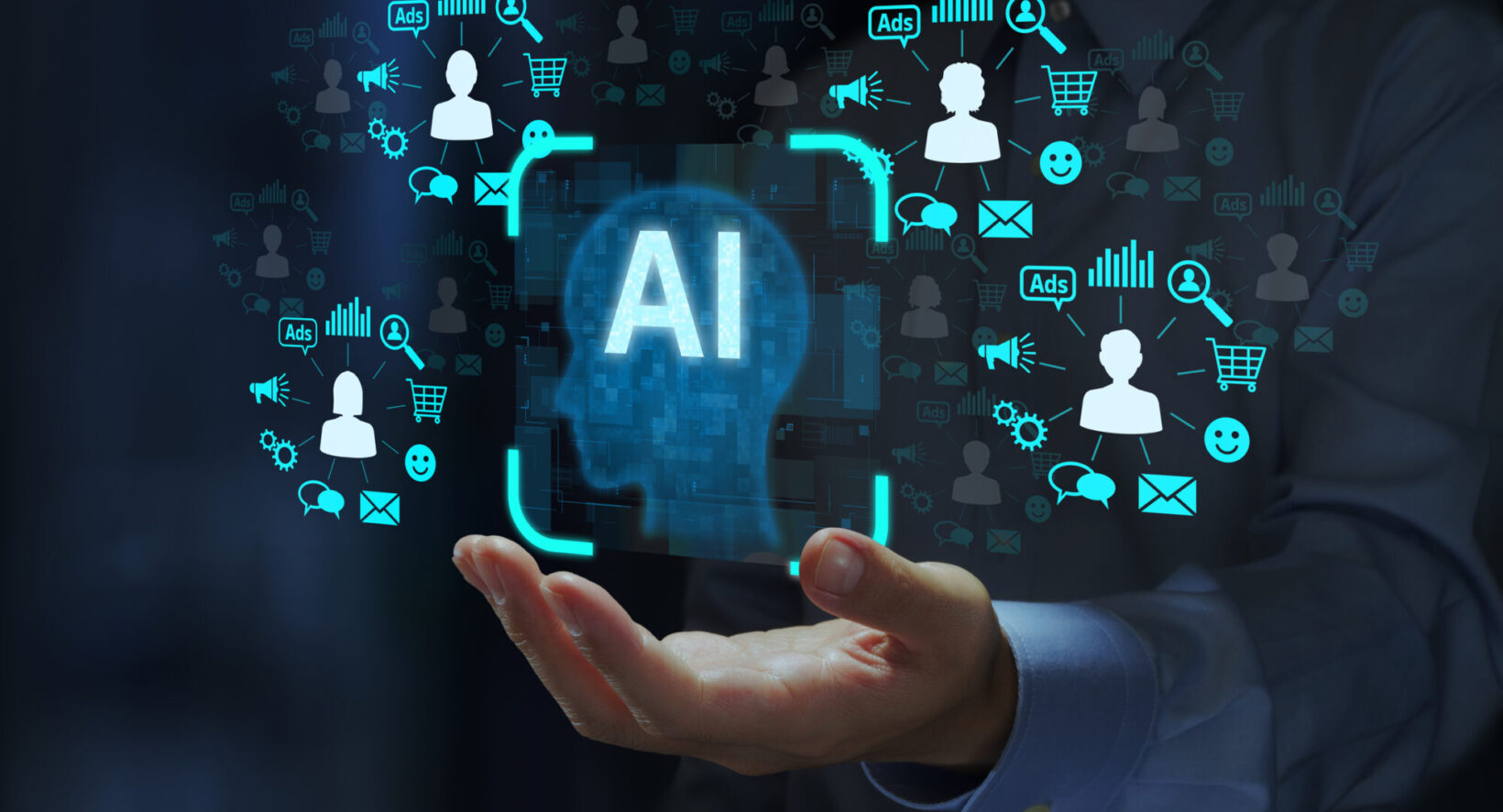DXを設計する ― 業務・人・システムをつなぐ全体設計の思想

-
インプットポイント
-
- DXの成功を分けるポイントを、設計という観点から理解できる
- 業務・人・システムの三要素を構造的に俯瞰して考える方法がわかる
- 経営企画・情報システム・運用など、DXを推進する立場で必要な視点を得られる
多くの企業では、DXがツール導入や業務効率化といった部分最適の取り組みにとどまりがちです。
しかしDXの成功を左右するのは、ツールではなく業務・人・システムの三要素をどう設計するかという全体構造の捉え方です。
本稿では、DXを「設計」という観点から見直し、成功の要否を分けるポイントや、経営企画・情報システム・運用部門など推進側の立場で持つべき視点を整理します。
- INDEX
第1章:設計思想がなぜ必要か
DXを導入プロジェクトとして進めると、次のような課題が起きやすくなります。
- 機能を盛り込み過ぎて導入までの期間が長期化する
- 使われない機能が増える
- 隣接する業務との接続が断たれ、二重入力や手戻りが出る
原因は、全体の設計図がないまま個別施策を積み上げているためです。
ここでの設計図とは、何を変えるか/どこから着手するか/隣接する業務とどのように接続するかをまとめたものです。こうした課題を防ぐには、個別の施策にとらわれず、全体をどうつなぐかという設計思想が欠かせません。
ただし、設計思想を機能させるには、何のために変えるのかというゴールを明確にすることが必要です。
ゴールが定まっていなければ、どんなに良い設計思想も方向を失い、施策は分散してしまいます。
DXのゴールは企業ごとに異なります。新しい収益源の創出、既存事業の磨き込み、働き方の見直しなど、目指す姿によって設計の重心は変わります。
<まとめ>
機能過多や使われない仕組み、業務の断絶といった混乱を防ぐためにこそ、
ゴールを定め、それを軸に全体を構想する“設計思想”が必要である。
第2章:DX設計を支える3つの重要要素:業務・人・システム
DXの設計を考えるうえで大切なのは、業務・人・システムを別々に設計しないことです。
この三要素は互いに影響し合う構造になっており、どれか一つを変えると、必ず他の要素にも波及します。
たとえば、業務の仕組みだけを改善しても、人の動き方が変わらなければ成果は出ません。
逆にツールを入れ替えても、業務フローが旧来のままでは、かえって混乱を生むことがあります。 ポイントは、三要素を「別々に最適化する」のではなく、「関係性として設計する」ことです。
【業務】:目的と流れを整理し、他業務との接続点を明確にする
- 目的:業務の流れを整え、情報の受け渡しをスムーズにする
- 起きやすい課題:プロセスの定義が曖昧で部門ごとに手順やKPIが不一致
- ポイント:自部門の完結ではなく、「次の工程」「隣の業務」との接続点を明確に設計する
【人】:仕組みを動かす人の役割・判断・権限を明確にする
- 目的:設計を日常運用に乗せ、改善を継続する
- 起きやすい課題:役割が曖昧、権限の明確化や教育が不足
- ポイント:役割・判断基準・教育計画を含めて設計する
【システム】:業務と人をつなぐデータ基盤を設計する
- 目的:データの流れを軸に、業務と人が連動する構造を設計する
- 起きやすい課題:部門ツールが乱立し、情報が分断される
- ポイント:業務の流れを止めないデータ連携と、変更・追加がしやすい構造に設計する
いずれか一要素だけを最適化すると、他に歪みが生じます。
業務を見直すときは、隣の業務や関係部門とのつながり、その中で動く人とシステムの設計までを同じ視点で考えることが重要です。
<まとめ>
部分最適ではなく、三要素をつなぐ全体設計を行うことでDXは機能する。
第3章:DX設計プロセス(手法と注意点)
ここで言う「DX設計」とは、システムや画面の仕様を固める工程に限らず、
DXを構造として実現するための上流工程(=要件定義~基本設計の前段)を指しています。
具体的には次のような構造的な設計を指しており、「なぜ・何を・どのようにつなぐか」を定義する上流の考え方として位置づけています。
- 業務設計:業務プロセスや接続点、KPI構造の整理
- 人の設計:役割・権限・判断基準・教育計画の定義
- システム設計:業務と人を支える仕組み・データ連携の設計
- 情報設計:データの発生・共有・活用の流れの整理
- 改善設計:PoCや定着を通じて、継続的に更新する仕組み化
上記の設計を実務として進めるための手順を整理すると、流れは大きく以下の4ステップです。
【1】(前提)As-Is/To-Beを整理する
DXの設計は、まず現状(As-Is)と理想(To-Be)を整理することから始まります。
このとき、業務フローだけでなく、業務・人・システムの関係性を含めて構造的に見える化します。
- 現状:何がどの順で行われ、どこに負荷や属人化があるか
- 理想:業務・人・システムが連動し、全体としてスムーズに機能する状態になっているか
- 差分:どの要素を優先的に変えるか(業務/人/システム)
この工程で大事なのは、「理想像」を描くことよりも、構造の差分を可視化することです。
どの部分を先に変えるかを明確にするだけでも、設計精度は大きく上がります。
【2】構造的な設計で「全体」と「接続」を描く
As-Is/To-Beの差分が見えたら、次に三要素の接続を設計します。具体的には、業務設計・人の設計・システム設計・情報設計・改善設計などを指します。
本フェーズのゴールは、「どの業務で情報が発生し、どこに渡り、誰が扱うか」を整理することです。
- 業務フロー図:上位の流れと派生業務の関係を整理
- 情報の流れ図:データの発生、共有、蓄積、活用までを明確にする
- 役割表(RACIなど):誰が実務を行い、誰が承認・改善を担うかを定義する
- KPIの連鎖図:経営指標から業務KPIまでを一貫して整合させる
- 改善フロー図:KPIの振り返りから課題抽出、施策やシステム改善の反映までの流れを明確にする
構造設計では、階層(業務・人・システム)と接続(流れ・責任)をセットで描くことがポイントです。
KPIや成果指標を部門間でそろえて設計することで、業務の方向性が定まりやすくなります。 これにより、「何を変えるか」だけでなく「どう動かすか」までが明確になります。
【3】PoC(概念実証)で「業務が回るか」を確認する
新しい構造を定義したら、小さく試すことで現場の実行性を確かめます。
PoCの目的は、単なるテストではなく、業務として成立するかを確認することです。
- 他業務と並行してPoCを行い、業務全体のリソースが回るかを確認する進め方が有効
- リソースが逼迫する場合は、既存業務の断捨離や自動化範囲の見直しなど、どの構造を調整するかを検討しながら設計を更新する
- ケースによって、顧客視点でのウォークスルーテストを行い、利用者の不便な点を洗い出して要件に反映する
PoCは「絵に描いた設計」を「現場で動く設計」に変えるためのプロセスです。
業務が止まらず回るかを確認することで、設計全体の精度が高まります。
【4】設計サイクルを小さく回す
DX設計は一度作って終わりではありません。
目的設定 → As-Is/To-Be → 構造的な設計 → PoC → 定着 の流れを3〜6か月単位で小さく回します。
サイクルを短く区切ることで、設計そのものを継続的に改善できます。
- 初期段階で完璧を目指さない
- 気づきや学びを設計図に反映させる
- 変化を前提に「更新できる設計図」にしておく
この考え方により、DXは「一度決めて終わり」ではなく、変化に適応し続ける仕組みへと進化します。
<まとめ>
As-Is/To-Be整理 → 構造的な設計 → PoC → 改善サイクルを繰り返し、現場で動く設計に磨き上げることが重要である。
第4章:推進体制と意思決定
設計は一部門で完結しません。
どれだけ設計図が整っていても、誰が意思決定し、誰が動かすかが曖昧だと現場は動きません。
ここでは、設計を実際に機能させるための推進体制を整理します。
【1】体制設計は「役割」と「決め方」の両輪で考える
DXを進めるうえで重要なのは、役割の明確化と意思決定ルールの設計です。
どちらか一方が欠けると、判断が止まり、プロジェクト全体のスピードが落ちます。
- 経営企画:目的・投資基準・横断的なKPIを設定する
- 情報システム部門:技術方針・共通データの定義・拡張性を担保する
- 運用部門:日常運用・教育・改善サイクルを回す
- 推進事務局(必要に応じて):全体の進行管理と意思決定支援を担う
各部門の責任範囲を整理したうえで、「どの決定を誰が行うか」を明確にします。
【2】設計図を「共通言語」として活用する
部門間で議論がすれ違うのは、「前提としている構造」が異なるためです。
設計図を共通言語として使うことで、部門をまたいだ議論がスムーズになります。
- 業務変更の優先順位をどう決めるか
- システム改修をどの範囲まで許容するか
- どのKPIを共通指標として追うか
これらを感覚ではなく、設計図に基づいて判断することで、議論が感情論ではなく構造論になります。
また、定例会議やレビューでは、設計図・データ・KPIを同じ画面上で共有すると、全員の視点がそろいます。
【3】意思決定を“早く、正しく”行う仕組みをつくる
DXでは、意思決定が遅れると構造全体が止まります。
スピードと正確さを両立するためには、決定ルールを先に設計しておくことが重要です。
- 変更の影響範囲を整理し、承認レベルを明確化する(例:軽微変更=部門長判断/重大変更=全体会議)
- 判断基準を明文化しておく(例:コスト・リスク・影響範囲の3軸で判断し、どのレベル以上なら経営判断に上げるかを事前に定義)
- 判断に迷った場合は、KPIや設計図を基準に優先順位を決める
こうした「決め方の仕組み」を整えておくと、属人的な判断を減らし、意思決定の透明性が上がります。
【4】現場が動き続ける“運用ガバナンス”を築く
設計が現場に浸透するかどうかは、運用段階のガバナンスにかかっています。
統制を強めすぎると現場の柔軟性が失われますが、緩すぎると再び分断が起きます。
- 定例レビューでKPI・改善点・変更要望を確認する
- 変更内容は設計図に反映し、常に最新版を共有する
- 小さな改善提案を吸い上げるチャネルを設ける
ポイントは、統制よりも接続を重視することです。
部門間をつなぐ「対話の場」があることで、設計思想が形だけで終わらず、実際の運用に活きてきます。
<まとめ>
設計を機能させるには、「誰が動かすか」と「どう決めるか」を明確にすることが欠かせない。
役割・意思決定・ガバナンスの仕組みを整えることで、設計思想が現場に根づき、DXは継続的に動き続ける。
終章:DXは「変化を設計し続ける」取り組み
DXは、ツールを導入して終わるものではありません。
業務・人・システムの三要素をつなぎ、変化を前提に設計を続ける取り組みです。
設計とは、未来を固定することではなく、変化に耐えられる構造を描くこと。
設計思想(構造を描く力)と接続思想(現場で動かす力)がそろったとき、DXは一過性のプロジェクトではなく、組織を進化させる”仕組み”へと変わります。
Profile

その後、デジタルマーケティング領域のコンサルティングファームにて、製薬・飲料・金融・サービスなど複数業界の マーケティング基盤構築や可視化プロジェクトをリード。2025年より株式会社ファーストデジタルにジョイン。