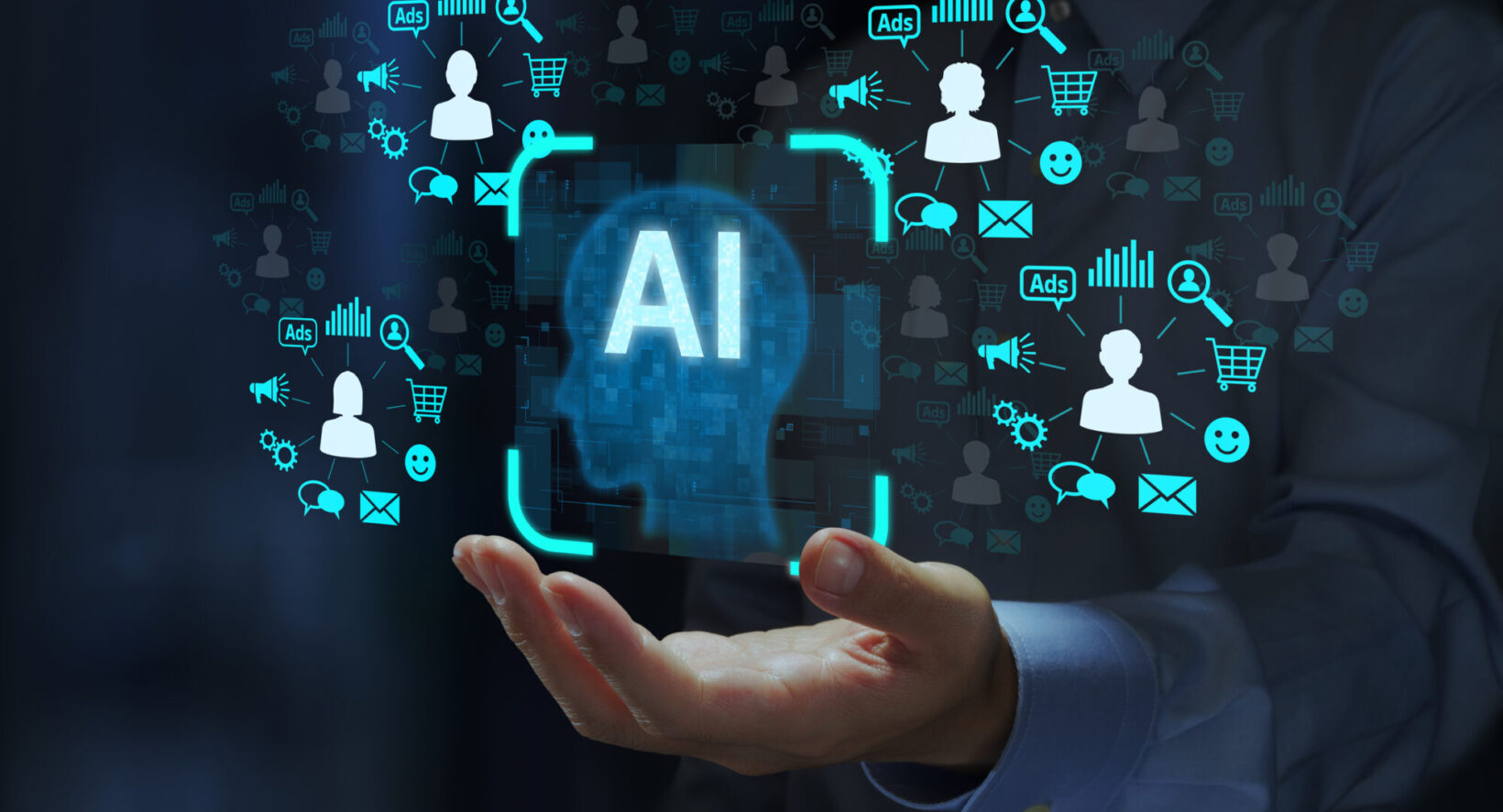【再現性の危機】心理学のビジネス活用における落とし穴

-
インプットポイント
-
- 心理学・行動経済学に潜む「再現性の危機」を理解できる
- 有名理論の信頼性を確認できる
- 心理学・行動経済学の活用で成果を出すための実践的な考え方がわかる
だれもが一度は聞いたことがあるであろう「スタンフォード監獄実験」。
監獄を模した環境に、ランダムに選ばれた看守役と囚人役を置いたところ、看守役が権力を乱用して虐待を行うようになったことから、「人は権威や環境の影響を受ける」ということを示した実験として有名です。ところが、別の研究者が同様の実験を行ったところ、結果は同じになるどころか、囚人が看守に立ち向かうという、まるで異なる結果になりました。すなわち「再現」しなかったのです。
このスタンフォード監獄実験のように、近年、いくつもの理論で科学的根拠が疑われ、「再現性の危機」として波紋を広げています。
一方、これまでビジネスでは、心理学や行動経済学の知見が意思決定や戦略立案に広く活用されてきたわけですが、これまで有効とされた理論が疑われる中、ビジネスパーソンはこれから何を信じ、どう実践すべきでしょうか。
本記事では、この「再現性の危機」の背景と問題点を解説し、ビジネスで応用されてきた代表的な理論と再現性の問題を紹介したうえで、心理学や行動経済学と今後どう向き合うべきかを考察。
人の意思決定や行動のメカニズムを解き明かそうとする心理学や行動経済学の知見は、本来、マーケティング、プロダクト開発、価格設定、交渉、チームマネジメント、採用、人材育成等、あらゆるビジネスシーンで味方となるはずです。
その科学的根拠や信頼性が揺らぐ中で、今後もこれらの科学・学問の知見をビジネスの現場で活かすためのポイントをお伝えします。
【目次】
- 再現性の危機とは
- 再現性が疑われている理論
- 再現性の危機を踏まえたビジネス実践論
- 終わりに
「再現性の危機」とは
ビジネスにおける心理学・行動経済学の重要性は明らかですが、今、その根拠となる研究の「再現性」に疑問符がついています。
この章では、「再現性の危機」とは具体的にどのようなものか、なぜ起きたのか、どのような対策が進められているのかについて見ていきましょう。
再現性の危機とは
そもそも「再現性」とは、同じ方法で誰が試しても同じ結果が得られることです。いうなれば信頼性のことです。
心理学や行動経済学等では、旧来から再現性の問題が指摘されてはいましたが、2010年代に入り、「再現性の危機」というフレーズで広く認識されるようになり、様々な分野で再現の失敗が報告されるようになりました。
特に、2015年の心理学大規模再現プロジェクト「Reproducibility Project: Psychology」では、心理学のトップジャーナルに掲載された研究100件を追試した結果、元研究の97%が統計的に有意な結果を報告していたにもかかわらず、追試で有意な結果が再現できたのはわずか36%にとどまったのです。
再現できなかった研究には、後述する「社会的プライミング」等、ビジネスの現場でも馴染みの深い理論が含まれており、信頼性が揺らいでいます。
再現性の問題を引き起こしているもの
なぜ、過去の研究結果が再現できないという事態が起きるのでしょうか。
指摘されているのは、研究の進め方そのものに関する問題です。例えば、統計的に「意味がある」とされる結果が出るまで分析方法を調整したり(p-hacking)、結果を見てから都合の良い仮説を後付けしたり(HARKing)、少ないデータだけで結論を出してしまったり、といった慣行が指摘されています。
また、「出版バイアス」の問題も指摘されています。出版バイアスは、学術雑誌が「新しい発見」や「効果があった」という研究を優先して掲載し、「効果がなかった」研究や過去の研究を検証するだけの研究は掲載されにくいというバイアスを指します。これにより、世に出る研究結果が、実際よりも効果を過大評価したものに偏ってしまう可能性があるのです。
信頼性を高めるための取り組み
この「再現性の危機」をきっかけに、研究の透明性や信頼性を高めるためのさまざまな取り組みが進められています。
例えば、研究を始める前に計画書(仮説や分析方法等)を公開する「事前登録」という仕組みがあります。これにより、研究者が結果を見てから都合よく計画を変えることを防ぎ、「効果がなかった」という結果にも価値があると考えられるようになってきています。
また、研究で使ったデータや分析手順等を公開する「オープンサイエンス」の取り組みも進んでいます。これにより、他の研究者が内容をチェックしたり、同じ研究を再現したりしやすくなります。
さらに、過去の研究が本当に再現できるのかを検証する大規模なプロジェクト「Reproducibility Project」等も行われています。
心理学や行動経済学を含めた「科学」が、問題を認識し、より信頼できるものへと進化しようとしている証と言えるでしょう。
ーーこのように、再現性の問題に対し、学術界では信頼性を高めようとする試みは既に始まっているわけですが、私たちビジネスパーソンとしては、「どの理論が要注意で、どの理論が信頼できるのか」を知りたいところです。
そこで次章では、マーケティング等のビジネスシーンで活用されてきた心理学・行動経済学の具体的な理論を取り上げ、問題点について見ていきましょう。
再現性が疑われている理論
人の意思決定や行動のメカニズムを解き明かそうとする心理学や行動経済学の知見は、マーケティング活動はもちろん、プロダクト開発、価格設定、交渉、チームマネジメント、採用、人材育成等、あらゆるビジネスシーンで味方となるはずですが、前章の通り、その根底にある科学的根拠が揺らいでいます。
この章では、ビジネスとのシナジーがある理論のうち、再現性の問題が指摘されている理論をご紹介します。
プライミング効果
プライミング効果は、先に見聞きした情報が、後の思考や行動に無意識に影響を与える現象を指します。
例えば、「温かい飲み物を持つと他者に温かい印象を持つ」といった研究が有名で、マーケティングにおける広告や、交渉術、職場環境のデザイン等への応用が期待されてきました。 しかし、特に社会的プライミング(例えば「高齢者を連想させるワードを見ると歩行速度が遅くなる」)では追試での再現が難しく、効果が非常に限定的であるとされています。
損失回避
同程度の利得と損失があった場合に、人は利得を得ようとするのではなく、損失の方を強く避けようとする心理傾向を指し、「損失は利得の2倍大きく感じる」とまで言われています。
この理論は、マーケティングの「期間限定割引」やビジネス上の意思決定、交渉、人事評価等に応用されてきました。
損失回避の傾向そのものは比較的有効だと考えられていますが、効果の大きさ(損失は利得の2倍)に疑念が唱えられており、損得が少額である等状況次第では、効果が見られないリスクがあるようです。
授かり効果
自分が所有しているモノを、所有していない同じモノよりも高く評価する傾向のことです。
無料トライアルや返金保証付きの販売等で、顧客に一時的な所有感を抱かせ、手放しにくくさせる施策として応用されることがあります。
損失回避同様、授かり効果についても、効果の大きさや現れる条件について疑問視されており、条件次第では当てはまらないケースがある点に注意が必要です。
パワーポージング効果
ビジネスに直接的に寄与する効果ではありませんが、間接的な効果を期待して実践されてきた理論として、「パワーポージング効果」をご紹介します。
パワーポージング効果は、自信のあるポーズ・姿勢を取ることが自信を高め、行動力等にプラスに働くとされる効果を指します。
集中力のコントロール等に利用してきたビジネスパーソンもいることでしょう。
ところが、元の実験では、テストステロンの値が上昇、コルチゾールの値が低下したとされていましたが、追試では、ホルモンレベルや行動への影響は再現されず、主観的な感覚への限定的な効果しか確認できませんでした。
ーーこのように、ビジネスの領域で「根拠」や「ヒント」として活用されてきた理論の中にも、再現性に課題を抱えている理論が含まれてることがわかりました。
当然、こうした理論に依拠して行われてきた意思決定や施策の有効性についても、改めて問い直す必要があるわけです。
再現性の危機を踏まえたビジネス実践論
数々の理論で再現性が疑われている心理学・行動経済学ですが、その知見が全て無意味になったということではありません。
本章では、今後ビジネスパーソンが心理学・行動経済学の知見とどのように向き合い、活用していくべきかについて考えます。
クリティカルな目線で最新動向を追う
当然ですが、新しい理論やキャッチーな理論を鵜呑みにしないことが重要です。
すぐに飛びつかず、「根拠は何か?」「再現性は確認されているか?」「どんな条件・状況での話か?」等、クリティカルに評価するといいでしょう。
また、これと相反するようですが、第1章でも触れた通り、研究手法の改善や透明化が進んでいるため、最新の研究動向や再現性に関する情報にアンテナを張り、過去の知見に固執せず知識をアップデートし続けることも必要です。
データに基づき効果を検証する
そもそも、多くの研究・実験は特定の条件下(参加者、状況等)で行われるため、効果はその「特定の条件」に依存します。
自社をとりまく固有の環境・条件(市場・顧客、競合、組織文化、従業員等)の下では、理論通りの効果が得られない可能性があります。
そのため、心理学や行動経済学の理論が自社のビジネスで有効かどうかを知るには、実際に試して効果を測定・検証することが不可欠です。
WebマーケティングにおけるA/Bテストはその代表ですが、営業施策の効果や社内制度変更の影響等、ビジネスにおける様々な場面で、データに基づき理論や仮説が正しかったかを検証し、「自社にとって最適な理論・方法論」を探る必要があります。
比較的再現性が確認されている理論を活用する
再現性が疑問視される理論が多い一方で、長年にわたり効果が安定して確認されており、ビジネスの礎として参考にできる理論も存在します。
効果の大きさや現れ方は文脈に依存するため、鵜呑みは禁物ですが、知識として持っておく価値はあるでしょう。
単純接触効果:
人や物事・情報等に繰り返し接触するだけで、それに対する好意が増す効果。広告やコンテンツ設計等に応用できます。なお、反復しすぎることで効果が薄れていくことも知られているため、注意が必要です。
系列位置効果:
最初と最後の情報が記憶に残りやすい効果。プレゼンテーションや報告書の構成等に活用できます。
チャンキング:
情報を意味のある塊に分けると理解・記憶しやすくなること。例えば、電話番号をハイフンで区切ると覚えやすいこと等が該当します。クライアント向けの資料作成や、顧客向けのコンテンツ設計等に役立ちます。
フレーミング効果:
同じ内容でも伝え方によって印象が変わる効果。例えば「成功率90%」と言うのか「失敗率10%」と言うのかで印象が異なることを指します。交渉、提案、社内外へのメッセージ発信等、あらゆるシーンで有効です。
ーー「再現性の危機」は、心理学や行動経済学との向き合い方を再考し、私たちの意思決定をより地に足のついたものに変えるチャンスと言えるでしょう。
終わりに
本稿では、ビジネスの領域で広く活用されてきた心理学や行動経済学の知見が、再現性の危機に直面している現状について掘り下げてきました。
再現性の危機は、心理学や行動経済学の有用性を否定するものではありません。
理論に安易に依存するのではなく、うまく向き合い取り入れることで、これからも、心理学や行動経済学の知見の恩恵を受けることができるはずです。
Profile