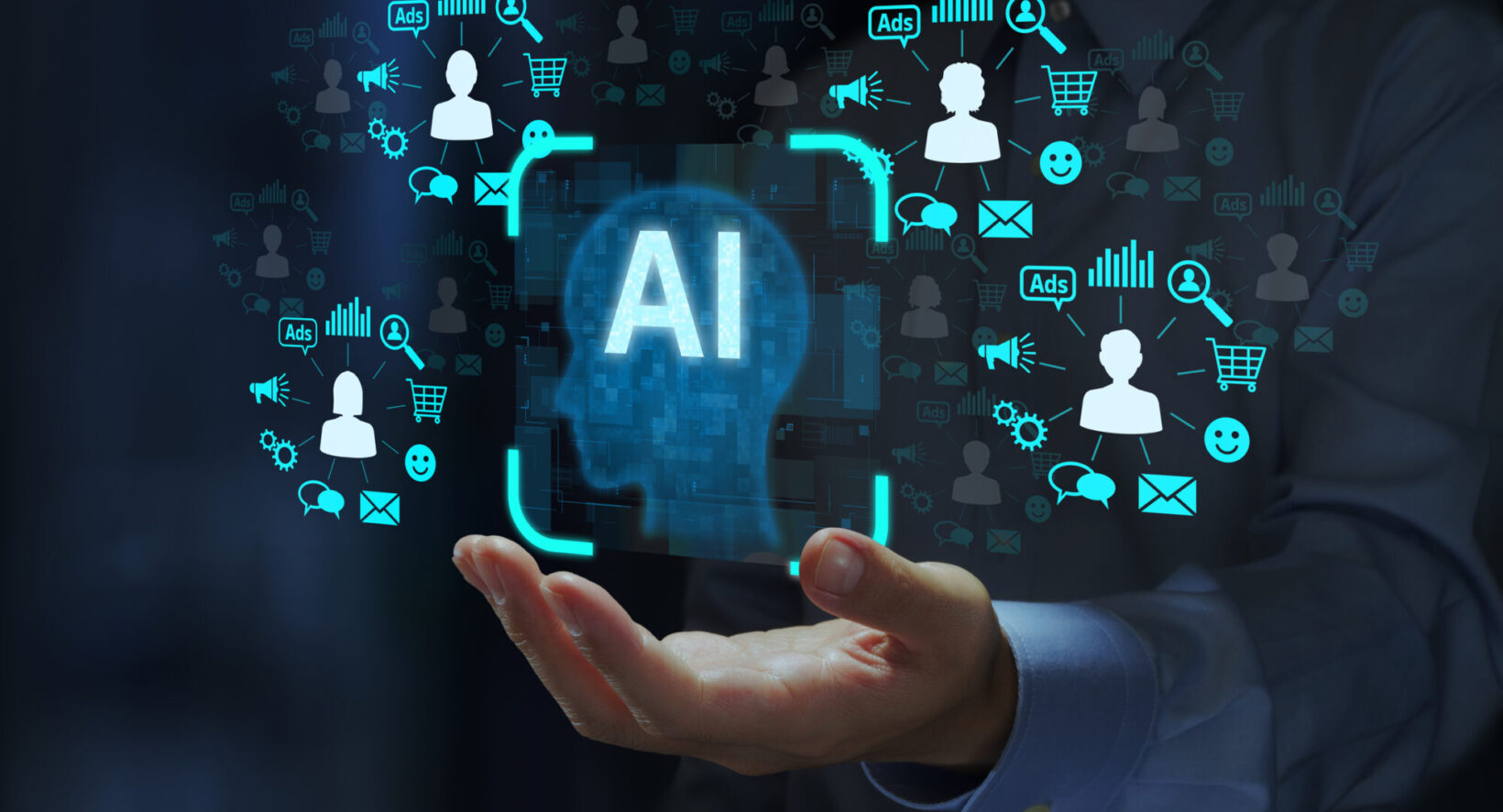【書評】ファンベース─支持され、愛され、長く売れ続けるために

-
インプットポイント
-
- ファンベースの重要性や効果がわかる
- ファンベースの構造や実践方法を体系的に学べる
- ファンベースとロイヤルティマーケティングの関係性を理解できる
情報環境の変化により、ブランドと顧客の関係は“点”ではなく“面”でつながる時代になりました。企業が一方的に情報を発信するのではなく、顧客が自ら参加し、語り、他者と共有することでブランドが広がっていきます。こうした時代には、販売促進よりも、顧客との関係そのものをどう育てるかが重要になっています。
その道筋を明確に示しているのが、佐藤尚之氏の著書『ファンベース─支持され、愛され、長く売れ続けるために』(筑摩書房[ちくま新書])です。著者は長年、広告・コミュニケーション領域で活動し、現在はファンを軸にしたマーケティング支援を行う実践者です。本書は、短期的な売上や話題づくりではなく、「長く売れ続ける関係づくり」に焦点を当て、ファンを中心に据えた新しいマーケティングの全体像を提示しています。
FD Magazineではこれまで、ロイヤルティマーケティングの基本概念から、NPS(ネットプロモータースコア)やRFM分析を通じた可視化手法、さらに「真のロイヤル顧客」を育成するための施策など、様々な角度からロイヤルティ強化の本質を探ってきました。
- 顧客と長期的な関係を築くロイヤルティマーケティングとは?
- マインドロイヤルティを可視化するNPS(ネットプロモータースコア)とは?
- ロイヤルティマーケティングを実践するには何をすればいいのか?
- ロイヤルティマーケティングのPDCAに役立つフレームワークとは?
- 「真のロイヤル顧客」の育成方法
- アクションロイヤルティを可視化するRFM分析とは?
- 顧客を惹きつけ、ロイヤルティを高める“コンテンツマーケティング”とは?
- 【書評】ぷしゅ よなよなエールがお世話になります
- 【書評】なぜ、Onを履くと心にポッと火が灯るのか?
今回は、その延長線上で「ファンの心理的支持をいかに育て、ブランドの持続的成長につなげるか」というテーマに焦点を当てます。本書は、「ファンの力を中長期的な企業成長の中心に据える」という発想を軸に、マーケティングのあり方そのものを再定義した一冊です。
ロイヤルティマーケティングの理論を“人の感情”という視点から深掘りすることで、本書は「ファンによる持続的なブランド支持」という、これからの時代に欠かせない実践的アプローチを提示しています。
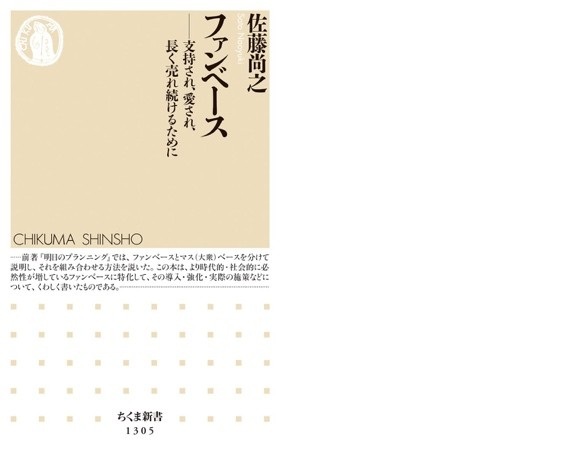
発売日:2018/2/10
著者:佐藤尚之
- INDEX
【書籍の全体像】ファンを中心に“長く売れ続ける”仕組みをどう構築するか
本書の構成は全六章です。第一章から第六章まで一貫して、「ファンを中心とした長期的な関係づくり」を軸に、企業がどのように“支持され続ける存在”になれるかを体系的に解説しています。
第一章では、キャンペーンや単発の施策が“一過性で終わってしまう”課題が提示されます。著者は、短期的な広告効果を追うあまり、長期的な信頼関係を築くことが後回しになっている現状を指摘します。そして、ブランドの持続的成長には「ファンを軸に据えた中長期的な施策」が欠かせないと述べています。
第二章では、「ファンベースが必然である三つの理由」が語られます。
- ファンは売上の大半を支え、伸ばしてくれる。
- 時代的・社会的に、ファンの存在がより重要になっている。
- ファンが新たなファンを作る。
著者はこの三つの理由を通じて、ファンが単なる購買者ではなく、“次の成長を生む源泉”であると示しています。これらは、ロイヤルティマーケティングの基盤にある「顧客生涯価値(LTV)」と密接に関係しています。つまり、ファンの存在は単にリピート購入を支えるだけでなく、共感による口コミ拡散を生み、企業に“持続的な売上構造”をもたらすのです。
第三章では、「支持を強くする三つのアプローチ」として、「共感」「愛着」「信頼」が紹介されます。
- 共感を強くする:ブランドの想いや背景を発信し、ファンが「共感できる物語」を共有する。
- 愛着を強くする:一貫した体験価値を提供し、「このブランドでなければ」と感じさせる。
- 信頼を強くする:約束を守り続け、誠実に対応する姿勢を積み重ねる。
これら三要素は「相互に作用しファンの支持を支える“心の土台”になり、顧客の購買行動を超えて“共感による継続的支持”を生む仕組み」と言えるでしょう。
第四章では、ファンの支持をより強固にするための三つのアップグレードとして、「熱狂」「無二」「応援」が紹介されます。
- 熱狂される存在になる:共感をさらに高め、ファンが自発的に語りたくなる体験を生む。
- 無二の存在になる:愛着を深化させ、他では代替できない個性を築く。
- 応援される存在になる:信頼を積み重ね、ファンが「支えたい」と思える存在になる。
この三つのステージを経て、ファンは単なる顧客から「ブランドの一部」としてのアイデンティティを持つようになります。つまり、ファンベースとは「ロイヤル顧客の集合体」であり、ブランドが長く愛され続ける基盤なのです。
第五章では、短期施策と中長期施策をどう組み合わせるかをテーマに、「全体構築の三つのパターン」が整理されています。
- 中長期施策のみで構築するパターン
最初からゆっくり中長期的にファンを増やしていくパターンです。
強力なブランド力を持ち、すでに一定数のファンが存在する企業に適しています。 - 短期・単発施策でファンをゼロから作っていくパターン
短期施策でまず認知度を上げ、それを元にすこしずつファンを増やしていくパターンです。
新ブランドやベンチャーに多く見られるアプローチです。 - 中長期施策を軸に、短期施策を組み合わせるパターン
短期施策を実行する以前から中長期施策を機能させておき、ファンのLTVを上げつつ、短期施策で相乗効果を狙うパターン。発売してそれなりに経った歴史あるブランドに適しています。
著者は、短期施策と中長期施策を相互補完的に設計し、ファンを中心とした全体構築を考えることの重要性を説いています。そして、その効果を測る指標として「NPS(ネットプロモータースコア)」が現時点で最も適していると述べています。(*NPSについての詳細は過去の記事で解説)
【ロイヤルティマーケティングとの接点】“共感・愛着・信頼”が生むロイヤルティ循環
ファンベースの構造を、ロイヤルティマーケティングのフレームと照らして見ると、両者の共通点が浮かび上がります。ロイヤルティマーケティングが「顧客のロイヤルティを高める」ための考え方であるのに対し、ファンベースはそのロイヤルティを「共感・愛着・信頼」という三層構造で分解し、より具体的な実践に落とし込んでいます。
この三つの要素は、さらに「熱狂・無二・応援」という上位概念へと発展します。
共感が深まれば、ブランドへの熱狂が生まれます。
愛着が高まれば、「無二の存在」として代替不可能になります。
信頼が積み重なれば、ファンはブランドを自ら応援するようになります。
つまり、ファンベースの構造は「共感→熱狂」「愛着→無二」「信頼→応援」という対応関係にあります。これは、ロイヤルティマーケティングの「マインドロイヤルティ(心理的ロイヤルティ)」の内側をより精緻に分解し、ファン心理の深層を可視化した体系といえます。
著者は、これらの関係性を定性的に捉えるだけでなく、NPSのような定量的指標で測定することの有効性にも触れています。そのため、ファンベースは単に感情を扱う理想論ではなく、ロイヤルティマーケティングのファネルをさらに進化させた実践的フレームといえるのです。
【実践に見るファンベースの効果】ファンが支え、広げ、育てていく循環構造
本書では、企業とファンの関係が「支える」「広げる」「育てる」という循環を持つことが繰り返し強調されています。ファンがブランドを信頼し、商品やサービスを継続的に選び続ける。その体験を他者に共有し、新しいファンを生む。この循環が、広告に依存しない持続的成長を可能にします。
この「循環の力」は、単なる口コミや共感を超えたものです。ファンがブランドの“共創者”となり、ストーリーや理念を共に育てていく。著者は、こうした関係性を築くことが、これからの企業に求められる最も重要な価値創造であると説いています。
ファンベースの実践は、売上を上げるための施策というよりも、ブランドの存在意義を再確認し、社員自身が誇りを持てるようになるプロセスでもあります。
【ファンベースがもたらす企業変革】“売らないマーケティング”への転換
本書は、単なるマーケティング理論書ではありません。著者が語るのは、ファンを「資産」として捉え、関係を“時間軸”で育てていくという経営思想です。
本書を通じて印象的なのは、「売るためにマーケティングをするのではなく、愛されるために活動を続けた結果、売れ続ける状態をつくる」という逆転の発想です。 従来のマーケティングが「顧客を獲得し、売上を最大化する」ことを目的としていたのに対し、ファンベースは「顧客と共にブランドを育て、支持を深める」ことを目的とします。結果として、売上やシェアは“成果”として後からついてくる。この価値観の転換こそが、ロイヤルティマーケティングの進化の先にある思想だと言えるでしょう。
企業がこの考え方を実践するには、まず内部文化の変革が必要です。短期的な成果を求めるKPI中心の評価制度を見直し、「ファンの声を聴くこと」「小さな共感を積み重ねること」に価値を置く仕組みを整えることが不可欠です。
さらに、ファンとの接点を担う従業員自身がブランドに誇りと共感を持つこと――いわば「インナーファンベース」の醸成も求められます。これが外部のファンベース形成を支える根幹になるからです。
このようにファンベースは、顧客接点・ブランド文化・組織構造のすべてを貫く「全社的ロイヤルティ戦略」として機能します。
短期的な成果にとらわれず、顧客との関係をじっくり築く。この思想は、ロイヤルティマーケティングにおける“信頼資産経営”と深く通じています。ファンベースはその精神を実践に移す具体的な方法論であり、ファンがブランドの成長を支え、さらに新しいファンを呼び込む「循環型の成長構造」を描き出しています。
まとめ
本書は、ロイヤルティマーケティングの本質を「人の感情」と「共感の連鎖」という観点から再定義した一冊です。短期的な売上目標や顧客獲得数を追う時代から、ファンと共に“長く愛されるブランド”を育てる時代へ――本書はその道筋を論理的かつ実践的に描いています。
企業が目指すべきは、顧客の数を増やすことではなく、既存のファンの支持を深めること。その積み重ねがやがてブランドの「熱狂」や「応援」を生み、新たなファンを自然と引き寄せていく。この循環こそ、現代のロイヤルティマーケティングが到達すべき次なるステージと言えるでしょう。
佐藤尚之氏が説く“ファンを中心に据えた経営思想”は、顧客ロイヤルティを軸とする企業にとって、今後の時代を生き抜くための最良の指針になるはずです。
Profile